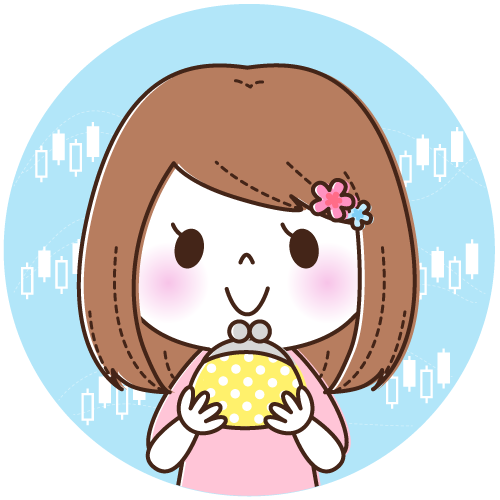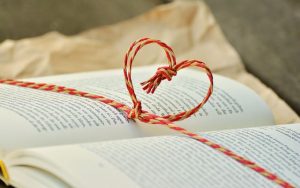投資の成果の80%や90%はアセットアロケーションで決まるといわれていますが、私はそう思ってません。
2007年頃に、当時マネックス証券にいらっしゃった内藤忍さんが書かれた資産設計塾という本を読みましたが、その本には銘柄選択・投資タイミング以外で投資の成果の80%は決まってしまうと書かれています。
当時はへぇ~、そうなんだ。と単純に考えてましたけど、今は考えは変わりました。
関係ないことだけど、内藤さんも今は変わってしまいましたね。ワインとか海外不動産を薦めるなんて。どうしちゃったんでしょうか?今だったら、絶対、彼の書いた本は買わないな…。
投資信託の積立やETFへの投資で資産形成しようとする人には、アセットアロケーションはとても大事なことなのでしょう。
でも、個別株投資を主にやっていると、幅広く世界中の株式に分散投資なんていろんな意味で難しくてできません。しかも、株式だけでなく、REIT、債券との組み合わせとか考えるのもしんどい。
だからもう、アセットアロケーションを考えるのはやめました(笑)
目次
アセットアロケーションを考えた投資でなくても大丈夫
投資にできるだけ時間をかけたくないのであれば、世界中の株式や債券に幅広く分散投資できるETFやインデックスファンドを利用するのは、とても賢い方法です。
プロが運用する大多数のアクティブファンドよりもインデックスファンドの方がリターンが高いという事実もありますし、ウォーレン・バフェットもS&P500に定期的に投資すればいいと発言しています。
インデックスファンドに定期的に投資すれば、「何もわかっていない」投資家でもプロの投資家以上の利益をあげることが実際に可能なのです。
逆説的ではありますが、「愚鈍な」カネがその限界を認識すると、もはやそのカネは愚鈍ではなくなるのです。
出典元:バフェットからの手紙
でも、
- 投資に時間をかけるのは苦行と思わない or むしろ好き
- 個別株投資の方が高いリターンも望める
このように考える人は、アセットアロケーションなんて考えずに、個別株投資でいいのではないかなと思います。
投資で成功したあとに、幅広い分散投資でリスクを低減させながら、市場平均の恩恵を受けられるような資産運用に移行すればいいんじゃないですか?
どこをゴールにするかによって違いますけど、資金が少ない間は、とにかく投資元本を増やすことに注力すべきなのではないかと考えてます。ゴールまでの距離が遠いのであれば、積極的な資産運用をしなければなりません。
10年以上セゾン投信や確定拠出年金の積立をやってみた素直な感想。
それは、投資信託では、なかなか増えないということ。
もちろん、リスクをとっているので預貯金よりはかなり高いリターンを得ることはできているので、その点では満足しているけれども、自分で運用している個別株投資と比べるとかなり見劣りします。
個別株投資で大金持ちになった人は多数いますが、投資信託で大金持ちになった人はいるのでしょうか?もし、いるのでしたら、ごめんなさい。
でも、投資信託の積立には大きなメリットもあります。
投資に興味のない人でも、積立を続けることで市場平均くらいのリターンを手に入れることが可能だし、30年も40年も続けていたら、それなりに大きな資産にはなっているでしょう。
ただ、超富裕層になりたいだとか、配当金生活を実現したいなどの大きな目標があるのであれば、インデックスファンドなどの投資信託の積立では無理だと思います。
ピーター・リンチが運用していた頃のマゼランファンドのような超絶リターンを叩き出すアクティブファンドに多額の資金を積立していれば、達成できるのかもしれないけれど、優秀なアクティブファンドは探すのも難しいですから。
理想とする資産運用のポートフォリオの作り方についてタイプ別に考えてみる

ポートフォリオを作るときに大切なのは、資産運用の目的は何なのか?ということを明確にすることです。
預貯金だと全くといっていいほど増えません。だから、少しでも増えればいいと考えているのであれば、株式の割合は少なくても大丈夫だろうし、リスクは積極的にとれるよという人は、株式の割合を高くすればいいのです。
投資目的も保有資産、年齢、家族構成などの投資背景も全く違うので、資産運用における理想的なポートフォリオは人によって違っていて当然で、誰にでも最適な割合なんてないのです。
だから、自分でしっかりと考えてポートフォリオを作る必要があるので、何冊か本を読んでからポートフォリオの作り方についての知識を身につけるとよいでしょう。
忙しいビジネスマンでも続けられる 毎月5万円で7000万円つくる積立て投資術は、今から投資を始めようとする方でも、簡単に読めると思います。
また、個別株投資を取り入れるのであれば、米国株式ブロガーにも大人気の株式投資の未来も大変おすすめの書籍です。
オススメ おすすめ書籍!株式投資をするなら読んでおきたい投資本
リスク許容度が高く、高リターンを望む場合のポートフォリオ
若くて独身という人は、積極型のポートフォリオにすることも多いのではないでしょうか。
米国を主にした外国株投資や日本株投資の割合を多くすれば、高いリスクと引き換えに高いリターンが期待できます。
私自身のポートフォリオのリスク資産は、日本株がほとんどで米国株式が2割ほど。
かなり積極型のポートフォリオになってます。銘柄分散はしているけれども、アセットクラスの分散はできていません。
またリーマンショック級の暴落がくれば、積極型のポートフォリオはかなりのダメージを受けるでしょうね。
2008年は先進国債券、金をのぞき、軒並みマイナスリターンでしたから。
| アセットクラス | リターン |
|---|---|
| コモディティ・金 | 5.5% |
| 先進国債券 | 5.3% |
| 国内債券 | 2.1% |
| 新興国債券 | -2.9% |
| ハイイールド債券 | -26.2% |
| 先進国株式 | -41.6% |
| 国内株式 | -41.8% |
| 国内REIT | -51.8% |
| コモディティ・原油 | -53.5% |
| 先進国REIT | -54.1% |
| 新興国株式 | -55.1% |
でも、暴落の後にはいつかは高リターンを叩き出すときが来ます。
2009年には下がり過ぎた反動もあったのかもしれませんが、新興国株式や原油のリターンは70%を超えてました。
でも、新興国株式や原油は70%越えのリターンを叩き出してますが、2008年に50%以上下落しているので2007年の水準は回復していません。(回復するには100%越えのリターンが必要)
一度、大きく減らしてしまうと、回復するまでが大変です。
だから、資産運用が好調な時も、どうやって今ある資産を守るか?ということを考えておいた方がいいです。
関連記事 安全で効率的な資産運用はないし、株式投資は簡単ではない。 関連記事 暴落は忘れた頃にやってくる!対処法を考えておこう。
リスク許容度が低く、低リターンを受け入れる場合のポートフォリオ
もう退職されているような場合は、リスクを抑えた資産運用になるかと思います。
国内債券を中心としたポートフォリオになるので値上がり益はあまり期待できませんが、リスクを抑えつつ利子や配当を受け取ることができます。
市場の暴落があっても、そこまでダメージを受けたくない人は保守的なポートフォリオが最適でしょう。
キャッシュポジション(現金)と投資の理想的な割合
投資をしていて難しいと常々思うのが、キャッシュポジションの割合です。
あまりにもキャッシュポジションを高くし過ぎてしまうと、今のような株式市場が好調なときには、よくいわれる機会損失ということになってしまいます。
しかも、受取配当金を増やしたいので売却し過ぎると配当金が減ってしまうし。
でも、キャッシュポジションがほとんどなければ、暴落したときに買えなくなりますし、本当に難しいです。
リーマンショックの時に投資口座にお金がなくて、国債や定期預金を解約してせっせと入金していたことを思い出すので、いつも一定の割合以上はキャッシュは残すようには心掛けています。
関連記事 キャッシュポジションの適正比率は?バークシャーと個人投資家では正反対に!
「100-年齢」を株式に投資するという説
よく言われるのが、資産のうちの「100-年齢」の割合だけ株式投資にまわしましょうということ。
たとえば20歳であれば、80%は株式投資に、残りの20%は債券投資ということです。
40歳であれば、60%は株式投資に、残りの40%は債券投資ということ。
バランスはとれているように思いますが、それなりにリスクがとれるのであれば、20代で独身なら100%株式投資でも問題ないような気もします。
「100-年齢」を株式投資の割合にするというのは、あくまでも目安です。もうちょっとリスクを低減したいのであれば、債券の割合を増やせばいいですし。
まとめ
結局のところ、資産運用のポートフォリオを作るとはいっても、理想的なバランスは千差万別。
臨機応変にキャッシュポジションの調整をする投資家もいれば、愚直に投資信託の積立を実行する投資家もいるし、暴落とか関係なしに保有して配当金再投資を続ける投資家もいます。
どれが一番いいのかは、わかりませんが、しっかりと自分の頭で考えて作ったポートフォリオであれば、たとえ資産運用に失敗しても得ることがあるはずなので、無駄にはなりません。
大事なのはマーケットから退場しないことと、納得のいく投資法に出会えるまで試行錯誤を繰り返しながら、投資の腕前を少しずつでもあげていくことではないでしょうか。
過去にもアセットアロケーションについて記事にしています。
関連記事 投資額に合わせてアセットアロケーションは変更するべき?
[最終更新日]: 2021/06/02